こんばんは。
元気に◎にじゅうまるブログのまさあきです。
今日は、中学生の子どもが勉強嫌いにならない様に「気を付けたい親の言動」について考えて行きましょう!もう直ぐ、学期末テストも始まりますので・・
思春期✖反抗期✖自我
まるでハンター✖ハンターのタイトルの様ですが、中学生の子どもが勉強嫌いになる第一歩は、親の一言が多いのではないでしょうか?
結論からお話しますと!
思春期の反抗期を経て自我(子どもから大人へ!)が目覚める!
自立が始まる時期なので親がああしろ!こうしろ!に反発します。例えると学期末の内申点で数学の内申が3だったら(親が考えるより低い場合)
「〇〇ちゃん!しっかりと勉強したの?」
「お母さんでも4、5は、取れたけど・・」
「国語は、4だから許せる範囲だけど・・」 ets・・・
学習要綱も2021年に大きな変革を遂げお母さん、お父さんの時代とは、難しさが違います。
塾の先生と話をして子どものテスト問題を見ても難しくなっているのはハッキリ分かります。
(徐々に微修正を行いながら1周りした4年目に今の形となったと聞きました。)
特に数学と英語は、5年前と比べても定期テスト形式で見れば、基本問題が少ないと感じます。
塾の先生もおしゃってましたが、日頃行われる小テスト、大きな定期テスト、科目ごとの提出物・・これらの総合計で5段階評価がされる訳ですが、4、5を取るのは難しいです。
私たちの頃や5年前までならば、定期テストの点数は大きなウェイトを占めていたのですが、現在では、25%くらいになっていると考えます。
※※2021年(中学校)に改正された新学習指導要綱について簡潔に記載します。※※
- 1、普段からしっかりと授業に取り組んで課題は具体的に根拠を持って書く。
- 2、小テストで高点数を取る。
- 3、グループディスカッションでしっかりと自分の意見を伝える。
- 4、定期テストで高点数を取る。
大きく分けてこの4項目となるのでそれぞれ25%くらいの配分になると考えます。定期テストの点数勝負だけでは、高い内申点は、取れない事が理解出来るでしょう・・
これでお母さん、お父さんも現在の中学生が置かれている状況を把握してもらえたかと思います。
学業の難しさと並行して思春期を迎えます(自我が目覚める)
「自分がこれから何をしたいのか?勉強だけしていても良いのだろうか?」
お母さんもお父さんも中学生の頃に何度も考えたりしたのでは?
でも、大人になって働いていると!もっと勉強をして難関大学に入っていれば・・社内で役職がもっと上がっていたのでは無いか?もっと年収が上がっていたのでは無いか?
だから、「勉強は、しっかりしないといけない!」、「難関大学に入学しないといけない!」
自分が、勉強をしなかった人ほど子どもには、「勉強をしなさい!」、「ゲームばかりしないで!」、「後で必ず後悔するからあなたは、親の言う事を聞いていればいいのよ!」・・・
と普段からの口癖になります。気をつけたい親の一言です!例外として子どもに自分が勉強を教えたり見てあげてる場合は、問題は無いです!教えながらフォロー出来るからです!!
毎回毎回、やる気が起こらない子どもに「勉強しなさい!」ばかり何もせずに言っていると子どもは、うんざりして反発します。
特に中学生の子どもには、一方的にこちらの(親の)要望だけを無理強いするのは止めて下さい。
気を遣う事とは違います!親が「何故?勉強をやらないのか?」について子どもから理由を聞いて親が子どもに分かる様に話し合ってみましょう!
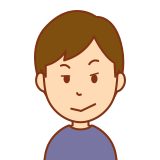
気が乗らないんだよねー!
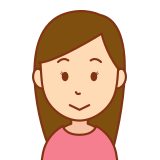
何が原因なのか?教えてくれない!
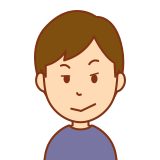
うーん!方程式が分からないから・・やる気が起きないんだ・・
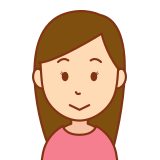
方程式かーじゃあ計算式を全て書いてどこで間違っているか一緒に見よう。
簡単に書きましたが、もっと複雑な場合もあります。大事なのは、話を聞いてあげて一緒に解決に向けて親からの提案を投げかけてみましょう!
決して、「じゃあ!こうしなさい!」などの行動を伴わないアドバイスは止めて下さいね!
一人で理解出来ない理由があって進める事が出来ないので「気が乗らない」のは良く分かります。
理解出来る様に一緒に教えながら進めて下さい!と言っても出来ない場合もあります・・
その場合は、「明日何時に勉強しよう」とするか!、今、一緒に調べながらするか!の2択で決めてあげて下さい。
教える場合は、しっかりと勉強して教えてあげて下さい。中学レベルならグーグルで調べながら学習すると理解出来ますので!頑張って下さい。
ここで大事な事は、『親が分からない箇所を一緒に考えてくれている事』の一点となります。
最後になりますが、中学の始めの段階で勉強を全くやらないのであれば、膝を突き合わせて話をするようにお願いします。時間が経てば経つ程、後になれば、やることが増えて勉強が本格的に嫌いになってしまいます。沢山、話をしてあげて下さい。
今日も最後まで読んで下さりありがとうございました。
